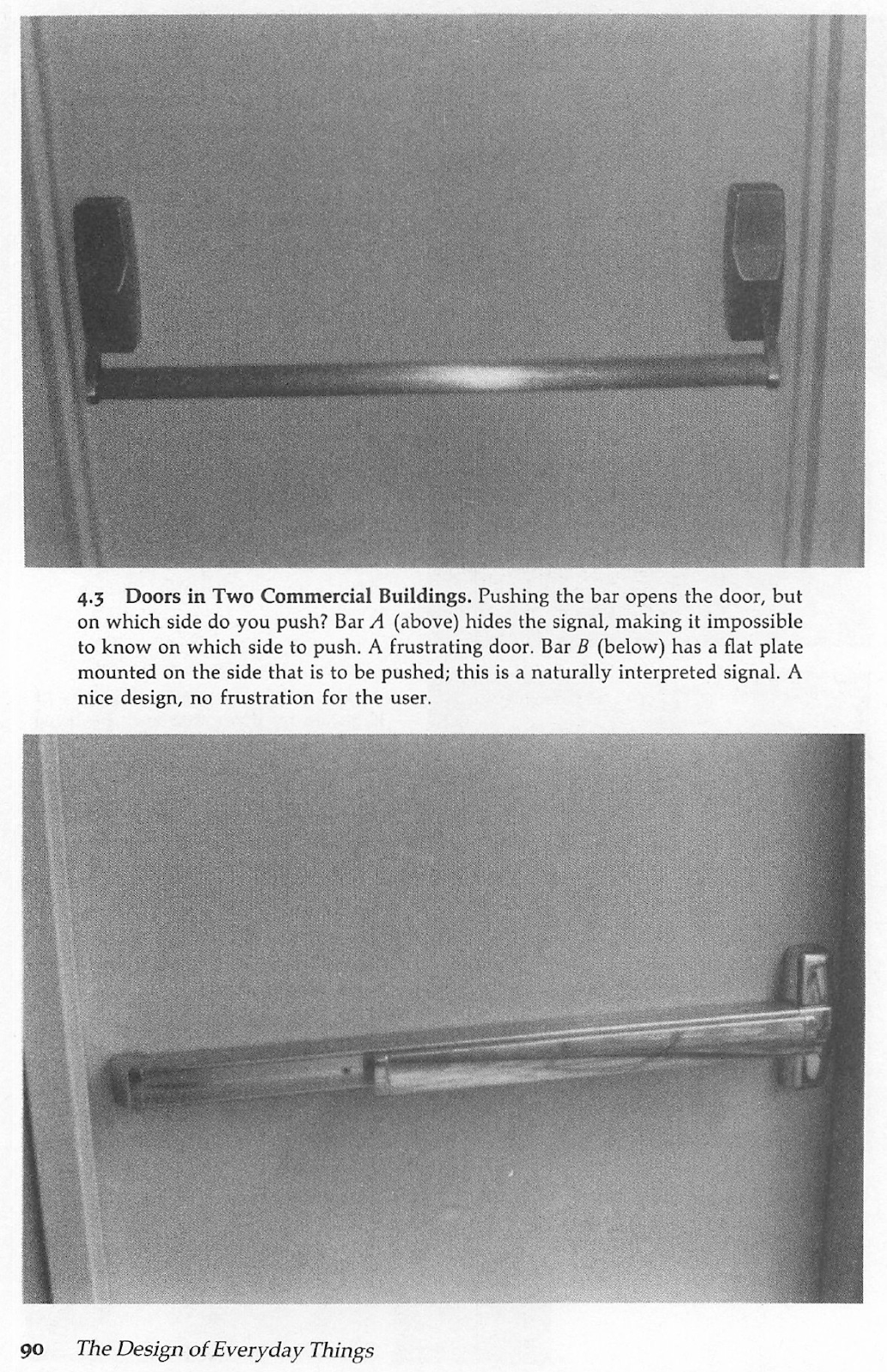2022年2月18日~19日に Twitter でつぶやいてたのをサルベージした:
悪口によって,(1) 標的になった誰かさんの地位だか格だかランクだかがほんとに下がるという主張と,(2) その人の地位 etc. が下であるように見せる・描き出されるという主張は,大きくちがう.「悪口はdegradeするよ」説はどっちを主張してるんだろ.https://x.com/optical_frog/status/1494609506952564736
あるいは,(3) 標的になってる誰かさんの地位を話し手が下に見ている態度を表出してるって説もありうるね.
https://x.com/optical_frog/status/1494609745684008962
『悪い言語哲学入門』では,特定の場面での「あんたバカァ?」は表出型の言語行為で,かつ,これは「社会的含意」として発語内行為または発語媒介行為として相手を「下に位置づける」って書かれてる.「下に位置づける」ってのは,さっきの (1) と (2) のどっちなんだろね?
https://x.com/optical_frog/status/1494614784922193920
どう定義するにせよ,悪口を言うって行為と,その行為で使われる言葉そのものを区別してほしい.「悪口リスト」は後者のリストだ.
「下に位置づける」事例がアニメの「あんたバカぁ」1個で,それが本当に事例になってるのかよくわからない.それに,他の事例とか反例になるかもしれないやつの検討とか,そういうのが一切ない.そこから罵りについて一般化してだいじょうぶなんだろうか.
https://x.com/optical_frog/status/1494983543390289921
この人は罵っていますか?罵っているなら,アーサー王のランクは下がってますか? https://x.com/optical_frog/status/1501124769252401154
この本の議論で,標的になった人物を「低く位置づける」のが発語内行為なのか発語媒介行為なのかはっきりしてないのは,前のツイートの (1) と (2) がはっきりしてないのと関連してる,と思う.
https://x.com/optical_frog/status/1494972515700989952
標的の地位・ランクをほんとに下げるんだとすると,それが発語内行為でなされるってのは,魔法みたいな話になる――その発語と同時に,必ず相手の地位・ランクが下がるってことだから.
https://x.com/optical_frog/status/1494973345653133312
「雨で洗濯物がずぶぬれになってるよ」って言葉を発すると,それと同時にぼくは断定って発語内行為をしたことになる.「明日,3時に品物をお持ちしますね」って言葉を発すると,それと同時にぼくは約束って発語内行為をしたことになる.
https://x.com/optical_frog/status/1494974586818940928
一方,洗濯物の話を聞いた相手が「ずぶぬれになってる」って信じたり,約束を聞いた相手が3時に自宅に待機したりするのが,発語媒介的な効果で,そうさせたって意味で発語媒介行為ってことになる.
https://x.com/optical_frog/status/1494975164424937475
発語媒介行為の方は,話し手が意図してることもあるし,そうでないこともある.それに,かならずその結果が起こる保証もない.断定すれば相手が必ず信じるなんて,おかしいでしょ.
https://x.com/optical_frog/status/1494975361787990016
洗濯物の話を聞いた相手がいっしょに急いで洗濯物を取り込みはじめたなら,それも発語媒介的な結果.場合によって,話し手はそれを意図してるかもしれないし,そうでないかもしれない.また,相手が手伝ってくれるとはかぎらない.
https://x.com/optical_frog/status/1494976693437534208
同書の議論をまずまず常識的なバージョンに解釈するなら,こう分ける手がある――
・発語内行為:相手の地位を低く *表現する*
・発語媒介行為:相手の地位を *ほんとに* 下げる(でも,そうはならないこともおおいにありうる)
https://x.com/optical_frog/status/1494977649768206338
というか,この本は発語内行為と発語媒介行為のキーワードをせっかく解説してるんだから,活用すればいいのに.
https://x.com/optical_frog/status/1494979781061799943
明らかに適合方向 (direction of fit) の話なんだけど,なんでここは専門用語を使わないんだろう.
https://x.com/optical_frog/status/1494982022904762374
「関係の向き」なんて変な言い方しなくていいじゃん.もしかして,セクハラでバークレーを追い出されたサールを参照したくなかったのかな.
https://x.com/optical_frog/status/1494983543390289921
言語行為論でオースティンとヴァンダーヴェーケンだけが出てきて,サールがまったく出てこないのは,なんらかの意図でそうしてるんじゃないかと思う.
https://x.com/optical_frog/status/1494984532373606401
ところで,悪態・罵りといえば,ピンカーせんせの『思考する言語』(The Stuff of Thought) がかなりまとまった議論をしてるんだけど,それは参照されてないんだな.ふしぎ.
https://x.com/optical_frog/status/1494622699708030976
この書評でも指摘されてた: 「これでは「悪口」が「ことば」なのか「言語行為」なのかよくわからないだろう」
https://x.com/optical_frog/status/1501128243478351877
ついでに,Claude 先生に上記の内容について感想を聞かせてもらった(こういうことを聞けるトモダチがいないから):
これらの投稿は、悪口の言語哲学的な分析について興味深い論点を提起しています。順を追って検討していきましょう。
まず、悪口による「地位を下げる」という行為の解釈について、3つの異なる捉え方が示されています:
- 実際に対象の社会的地位を低下させる(事実の変更)
- 対象を低い地位にあるように描写する(表象の操作)
- 話者が対象を低く見ている態度を表出する(心的状態の表現)
これらは概念的に異なる作用を指しており、『悪い言語哲学入門』での「下に位置づける」という表現の曖昧さを指摘する重要な区別だと考えられます。
特に、「あんたバカァ?」という発話を「表出型の言語行為」としつつ「社会的含意」として「下に位置づける」と説明する部分は、(3)の態度表出と(1)または(2)の社会的効果を混在させている可能性があります。
また、投稿者は悪口を「行為」と「言葉そのもの」に区別すべきだと指摘しています。これは言語哲学における重要な区別で、例えば:
- 言葉そのもの:語彙的な意味や社会的な含意
- 行為:特定の文脈での使用や意図された効果
最後に、Pinkerの『思考する言語』への言及がないという指摘は興味深いです。言語学的な観点からの悪口の分析も、この議論に有益な視点を提供できたかもしれません。
結論として、これらの投稿は『悪い言語哲学入門』の分析における概念的な曖昧さを指摘しつつ、悪口の言語哲学的分析においてより精緻な区別が必要であることを示唆しています。特に:
- 社会的効果の種類の区別
- 言葉と行為の区別
- 既存の言語学的研究との対話
これらの点について、より詳細な検討が望ましいと言えるでしょう。